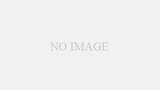愛児園の卒園式を終えて、約1週間が過ぎました。
5年前、愛児園のホームページを見て『こんな素敵な園に我が子が通えたらどんなに嬉しいだろう』と思いを馳せていたことを昨日のように思い出します。
4年間、本当にお世話になりました。
日頃から『私たちも愛児園に通いたかった』とつぶやいている私たち夫婦ですが、改めて愛児園のすばらしさを先日語り合っていたところです。
HPを見てくださっている未来の愛児園っ子の保護者様も意識しつつ(笑)私たち家族が大好きな愛児園の素敵な所を書かせていただけたらと思います。
(たくさんありますが敢えて3つに絞ります)
1つ目めは、園全体が『モンテッソーリ教育』という土台の上で成り立っているということです。
モンテッソーリ教育、というと【おしごと】を意識される方も多いと思いますが、園生活は【おしごと】だけではありません。
園長先生が朝玄関で迎えてくださり、あいさつをするところから、お仕事、着替え、チャペル、昼食、歌、合奏、体操、お友達との関わりなど全て、モンテッソーリ教育を土台にした生活は、広がっています。
例えば、傘を畳むこと、自分の荷物は自分でもつこと、例え子どもにとって困難なことがあったとしても、先生方は【自立できるように】その子一人一人の『(やりすぎでもない、足りない、でもない)本当に必要な助け』を考え、「支え」「導いて」くださいます。
愛児園には何人かの先生がいらっしゃいますが、どの先生もその子一人一人をよく見て、対応していただいているところには本当に頭が下がります。
それは、プレクラスのN先生からのノートからもよくわかります。
プレさんの時からたくさんの先生方がきめ細やかに子どもを見てくださいます。
2つ目は、園と保護者が共通の認識をもって子どもと接することができるよう、先生方が工夫してくださっていることです。
愛児園には、お母さんたちが集まって園長先生とモンテッソーリ関連の本を読む「読書会」(任意参加)、園長先生のお話を聞く「ハンナの会」とお父さんも参加する「保護者会」があります。
ここで、私たち親は、園でどんなことが行われているのか、「モンテッソーリ教育の考え方を家庭でも取り入れる場合はどうしたらよいのか」具体的にとてもわかりやすく教えていただきます。
子育てをしていると、毎日があっという間に過ぎていきますが、こうやって時折自分たちのことを振り返り、また、夫婦で話し合う機会を頂けることは、とても貴重なことでした。
夫婦で共通認識の元、子どもたちとも話ができたので、子どもとの意思疎通が楽になりました。
3つ目めは、環境の素晴らしさです。
愛児園には四季折々のお花や果物、野菜が育ちます。
教会の方や園のスタッフの方々が大切に育ててくださっています。
(我が子はとれたてのスナップエンドウを園でいただいてから、スナップエンドウが大好物になりました!)
朝は、モッコウバラの素敵なゲートで園長先生が迎えてくださり、四季折々の草花に囲まれながら、お友達と園庭で遊び、時にジャガイモを植えたり、レモンやオリーブ、ブドウがなる様子を見たり、ミカンを採ったりと、自然豊かな生活を過ごすことができます。
愛児園の子どもたちは、身の回りにある自然に関心を向け、また大切にする心が育っています。
このような素敵な愛児園で過ごした一日一日は、親子共々、かけがえのない大切な日々でした。
その思い出は先生方の笑顔と共に、心豊かに思い出されます。
「初めてのことは苦手」「苦手なものは取り組みたくない」我が子でしたが、先生方は「成長の過程」と捉え、スモールステップで子どもを導いてくださいました。
そして、根気強く取り組んだお仕事、モンテッソーリ教育という大きな土台の元過ごした毎日・・・そういった1つ1つの積み重ねにより、我が子は今、少しずつ「やればできる」「がんばってみる」という姿を見せてくれ始めています。
これからどんな成長が待っているか楽しみで仕方がありません。
大切な幼児期にこのような素晴らしい園で過ごせたことは、私たち家族にとって、大きな糧となっていくと思います。
これからもたくさんのお子さんたちが愛児園に出会い、それぞれの個性を生かし生きていくことができますように・・・そして、子どもたちが大きくなってもいつでもまた愛児園という場所に帰ってくることができますように・・・心からお祈りしています。
4年間、本当にありがとうございました。